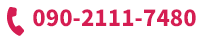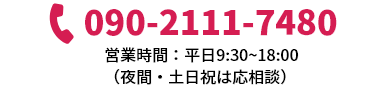【千葉 社労士】発達障害の方の「生きづらさ」を支える障害年金のはなし
はじめに
「職場でのコミュニケーションがうまくいかない…」
「集中力が続かなくて仕事でミスを繰り返してしまう…」
「人混みや大きな音が苦手で外出がつらい…」
発達障害(ASD・ADHD・学習障害など)の特性により、日常生活で多くの困難を感じている方は少なくありません。そんな「見えない困りごと」を抱えながら生活している方に、知っていていただきたい制度があります。それが「障害年金」です。
発達障害でも障害年金はもらえます
多くの方が「発達障害では障害年金はもらえない」と思い込んでいますが、これは誤解です。
障害年金の対象となる発達障害
- 自閉スペクトラム症(ASD):コミュニケーションの困難、こだわりの強さ、感覚過敏など
- 注意欠如・多動症(ADHD):不注意、多動性、衝動性による生活への支障
- 学習障害(LD):読み書きや計算など特定分野の著しい困難
これらの特性が、日常生活や仕事にどれだけ影響を与えているかが評価のポイントです。
受給できる条件
1. 初診日の条件
発達障害の症状で初めて医師にかかった日が「初診日」となります。
初診日のパターン
- 20歳前:保険料を払っていなくても受給可能
- 国民年金加入中:保険料の納付状況が問われる
- 厚生年金加入中:より手厚い給付が受けられる可能性
2. 障害の程度
日常生活や仕事への支障の度合いで判定されます
1級(月額約8万4千円)
- 日常生活で常に誰かの援助が必要
- 一人で外出することが困難
2級(月額約6万7千円)
- 日常生活に著しい制限がある
- 働いて収入を得ることが困難
3級(厚生年金のみ・月額約5万円)
- 労働に著しい制限がある
- 限定的な環境でのみ就労可能
3. 判定のポイント
IQ(知能指数)だけでなく、以下の点を総合的に評価します
- コミュニケーション能力
- 対人関係の築き方
- 日常生活の自立度
- 仕事の継続性
発達障害特有の申請のポイント
1. 「見えない困難」を具体的に伝える
発達障害の困りごとは外からは分かりにくいものです。以下のような具体例を詳しく説明することが大切です
日常生活での困りごと
- 買い物でパニックになる
- 電話対応ができない
- スケジュール管理ができない
- 感覚過敏で電車に乗れない
仕事での困りごと
- 指示を理解できない
- 同じミスを繰り返す
- 職場の人間関係で孤立する
- 転職を繰り返している
2. 就労していても諦めない
「働いているから障害年金はもらえない」は間違いです。以下の点が考慮されます
- 仕事の内容(簡単な作業のみか)
- 職場での配慮(障害者雇用かどうか)
- 勤務時間(短時間勤務か)
- 継続性(頻繁に転職していないか)
- 収入額(生活できる水準か)
3. 二次障害も重要な要素
発達障害の特性からくるストレスで、以下のような二次障害を併発することがよくあります
- うつ病
- 不安障害
- 適応障害
- 睡眠障害
これらも含めて総合的に評価されるため、隠さずに伝えることが重要です。
よくある質問
Q1. 大人になってから発達障害と診断されました。障害年金は対象になりますか?
A1. はい、対象になる可能性があります。大人になってから診断されても、子どもの頃からの困りごとが続いている場合は申請できます。ただし、初診日の特定や保険料の納付状況が重要になります。
Q2. 療育手帳を持っていないと申請できませんか?
A2. 療育手帳は必要ありません。療育手帳と障害年金は別の制度です。発達障害の診断があり、生活に支障があれば申請可能です。
Q3. 複数の発達障害があります。どのように評価されますか?
A3. ASD・ADHD・学習障害など複数の特性がある場合は、それらを総合的に評価します。それぞれの特性がどのように生活に影響しているか、具体的に説明することが大切です。
Q4. カウンセリングしか受けていませんが、申請できますか?
A4. 医師による診断と診断書が必要です。カウンセラーは診断書を作成できないため、精神科や心療内科を受診して正式な診断を受ける必要があります。
申請の流れ
1. 相談・情報収集
- 年金事務所で制度の説明を受ける
- 必要書類を確認する
2. 初診日の証明
- 最初に受診した病院で「受診状況等証明書」を取得
- カルテがない場合は代替資料を探す
3. 診断書の取得
- 現在の主治医に「精神の障害用診断書」を依頼
- 日常生活の困りごとを具体的に伝える
4. 申立書の作成
- 生まれてから現在までの状況を時系列で記載
- 具体的なエピソードを交えて困りごとを説明
5. 申請・審査
- 必要書類を年金事務所に提出
- 3~6か月程度で結果通知
専門家に相談するメリット
発達障害の障害年金申請は複雑になりがちです。社会保険労務士などの専門家に相談することで
- 初診日の特定をサポートしてもらえる
- 「見えない困難」を適切に書類に反映できる
- 複雑な手続きを代行してもらえる
- 受給の可能性を高められる
- 精神的な負担を軽減できる
などのメリットが存在します。
まとめ
発達障害の特性による「生きづらさ」は、周囲からは理解されにくいものです。しかし、障害年金は、そんな困難を抱えながら生活している方を経済的に支える大切な制度です。
「自分は対象外かも」「手続きが難しそう」と諦める前に、まずは情報収集から始めてみませんか。一人で悩まず、年金事務所や専門家に相談することで、新しい道が開けるかもしれません。
あなたの「生きづらさ」が少しでも軽くなり、より安心して生活できる未来への一歩を踏み出してください。
この記事を書いた人

- 社会保険労務士
-
はじめまして。社労士事務所フィル・エンドランの黒田隆治と申します。
私は障害年金のサポートを通して、生まれ育った地元・船橋、習志野の地域で暮らす皆さまの力になりたいと考えています。
障害年金の申請は一人で抱え込むと不安が大きく、途中で諦めてしまう方も少なくありません。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
最新の投稿
- 8月 5, 2025コラム【千葉 社労士】発達障害の方の「生きづらさ」を支える障害年金のはなし
- 8月 5, 2025コラム【千葉 社労士】知的障害のお子さんの将来を支える「障害年金」の基礎知識
- 8月 5, 2025コラム【千葉 社労士】統合失調症でも障害年金はもらえる?知っておきたい基本のこと
- 8月 1, 2025コラム【千葉 社労士】うつ病でも障害年金がもらえるって本当?
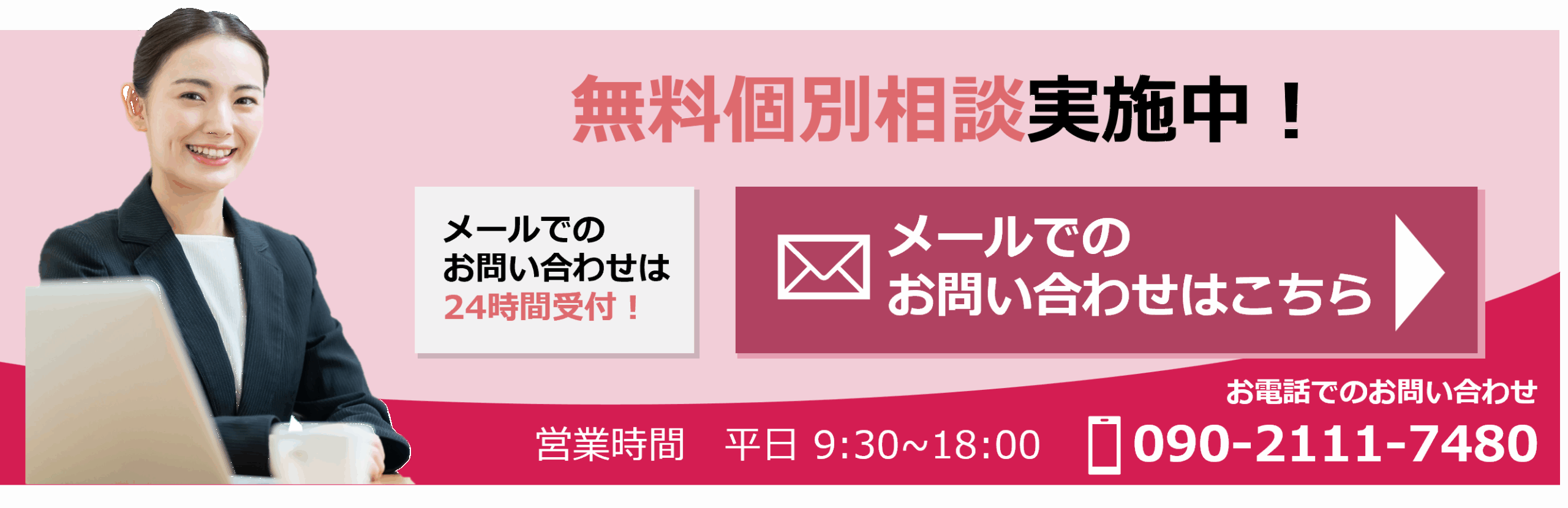

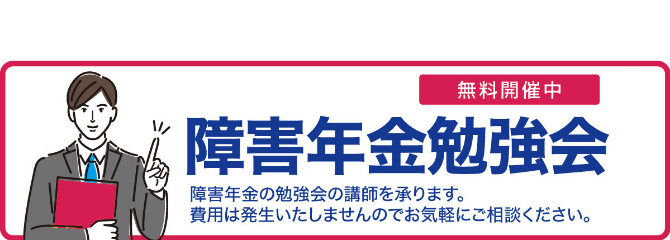

 初めての方へ
初めての方へ